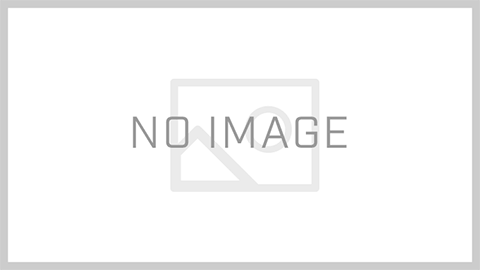記事では、ネットワークが生まれた背景と、進展をたどります。ネットワークは、計画的に生まれたものではなく、情報交換などの必要性にせまられて生じました。ネットワークの歴史をたどることで、曖昧で判りにくいwebの世界を身近に感じられるでしょう。
サーバーネットワークの歴史
技術の進歩とともに、コンピュータ(PC)とプリンタを接続しただけのスタンドアロンシステムは、明らかに無駄が多い方式です。そのため、コンピュータ同士を接続するのに効率の良いサーバーネットワーク方式が生まれました。
先ずは、コンピュータが独立で動く、スタンドアロンシステムの歴史から紹介します。
スタンドアロンシステムが産まれた背景
スタンドアロンシステムは、1970年代の汎用コンピュータやPC(パソコン)が登場した時に、特定用途の演算処理を行うために出来上がりました。
- この時、標準的なMS-DOS、UNIXなどのOS(オペレーティングシステム)が登場します。OSが生まれると、OS上で動作するワープロや表計算システムなどのソフトウェアが提供されるようになります。このソフトウェアのおかげで、利用者はデータを入力するだけで、直ぐに結果を得られるようになります。
- この時代のコンピュータには、ハードディスクが無いため、ソフトウェアやデータは、フロッピディスクなどの補助記憶デバイスで管理していました。
- コンピュータで行う業務は、ドキュメント処理が主体のため、プリンタ接続は必須でした。
当時のスタンドアロンシステムは、コンピュータ(PC)とプリンタを接続したものを、利用者ごとに用意したものでした。
やがて、PC(パソコン)の補助記憶装置は、内蔵型のハードディスク(HDD)が主流になっていきます。ハードディスクは、巨大な記憶容量を持っているため、ソフトウェアごとに、フロッピディスクを用意する必要性は無くなります。
コンピュータ同士を接続した、サーバーネットワークの登場
PC(パソコン)は、内蔵型のハードディスク(HDD)が主流になってきて、フロッピディスクはいらなくなります。しかし、契約書や、あいさつ文、表計算の集計表などのように繰り返し使うものは、特定のフォーマットがあると便利です。
そのため、フロッピディスクは残存しますが、フロッピディスクの使いまわしは不便です。また、プリンタを一人1台使うのは無駄でしょう。コピー機やファクシミリなどは事務所で共有するのが普通だからです。
そこで生まれたのがデータの共有化という考え方です。
技術の進歩と共に徐々に複数のコンピュータで、1台のプリンタをネットワーク接続するようになります。
複数のPCと1台のプリンタを配線で接続するのは合理的ですが、接続の仕方によっては副作用もあります。接続されるコンピュータの台数によって、最適な手法が次々に生まれて活用されていきます。
まとめ
コンピュータの世界で、スタンドアロンシステムが始まると、さらに無駄のない方法を模索するようになります。
小規模環境で活用されたピア・ツー・ピア方式
プリンタの共有や、データのやり取りを簡便にする、ピア・ツー・ピアは、双方のPC内に資料やデータを置く方式です。つまり、、ピア・ツー・ピア方式は、家庭内などの小規模の場合に有効でした。
その為、ピア・ツー・ピア方式が使われるのは、家庭内などの小さくて、個人的なネットワーク内だけです。
大規模環境で必須のサーバーネットワークシステム
大規模なシステムでは、必要性に迫られてサーバーネットワークシステムが登場します。
そして、サーバーネットワークシステムは、webの発展に寄与していきます。
簡素な窓をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。